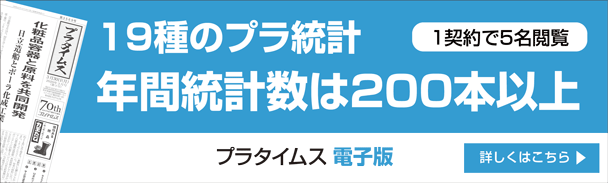*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。
*記事で使用している図・表はPDFで確認できます。
シリーズ連載① ポリマーの接着と分析講座
No.5 接着分析に用いる分析手法①
ジャパン・リサーチ・ラボ代表 奥村治樹
前回までは、主に接着のメカニズムや解析の考え方について解説した。今回から数回は、解析を実際に行っていくにあたって必要不可欠となる分析手法について、表面分析を中心として代表的なものをピックアップして解説していく。
1.接着分析に用いる分析手法
接着では様々な分析手法を用いる必要があるが、接着メカニズムの解明、剥離原因の解明など全てにおいて欠かすことができないものとして表面分析が挙げられる。この理由は明白であり、接着が表面、界面現象だからである。表面分析と一言で言っても様々なものがあることは周知の通りである。今回ではそれらの中で、特に接着分析、剥離分析において重要となる代表的なものをピックアップして解説する。
表1は、接着分析、剥離解析で用いられることが多い代表的な表面分析手法をまとめたものである。もちろん、これら以外の分析手法も用いられるが、少なくともこれらは欠かすことができないものであると言える。表中のプローブとは、スペクトル等の情報を得るための励起源等として何を用いているかを、検出信号はその励起によって放射される検出対象は何を用いているかを表している。
表を見ると分かる通り、電子を励起源としているオージェ電子分光法や電子線微小部分析法、走査型電子顕微鏡は面内(空間)分解能が他に比べて高い。これは、プローブである電子は電場レンズ等によって微小ビームに収束できることによる。これに対して、X線を励起源に用いるX線光電子分光法の面内分解能はそれほど高くない。これは、通常の実験室用の設備ではX線を十分に集光することが困難なことによる。ただし、放射光等の施設を用いればこの限りではないが、ここでは一般的に平易には使用できないので説明は割愛する。そして、可視光領域近辺の光を用いるレーザーラマン分光法やフーリエ変換赤外分光法はこれらの中間的な面内分解能を有している。したがって、目的とする対象領域の大きさによって使い分けることになる。
検出信号と得られる情報を見ると、電子線やX線を検出信号としている手法は主に元素に関する情報を得られることが分かる。これは、それらの検出信号が元素そのものに起因することによる。これに対してラマン分光法や赤外分光法等の可視光近辺の光を検出信号として用いている手法では主として、官能基等の構造に関する情報を得ることができる。それらの検出信号が化学構造等の原子団に局在化している振動に由来することによる。
測定深さについては、プローブや検出信号の浸透または脱出深さによって決まっている。例えば、X線光電子分光法の場合には、検出信号である光電子の対象物質内での平均自由行程によって決まっている。
このように表を詳細に見ていくと、一つの結論を得ることができる。それは、「万能な手法は無い」ということである。分解能や感度も高く、元素情報から構造情報、果ては形態情報まで全て得られるというような手法は残念ながら存在しない。したがって、手法選択において重要なことは、何を最も優先するかということをしっかりと考えることであると言える。対象物が微小なものであれば、どうしても面内分解能を優先することにならざるを得ないので、他のものについては諦めることも必要になる場合もある。何を知りたいのかということを考えることが手法選択の第一歩である。
以降では、表中の手法の中からピックアップしながら、個々に詳細に解説していく。
2.X線光電子分光法(XPS、ESCA)
XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)やESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)と呼ばれている手法である。X線光電子分光法(XPS)の原理は、超高真空中で試料にX線を照射し、放出される電子(光電子)を検出する(図1)。放出される光電子は、対象となる原子の内殻電子に起因するものであり、そのエネルギーは元素ごとに定まることから、エネルギー値を知ることで定性分析を行うことができる。励起X線としてはAlやMgのKα線など比較的低いエネルギーのものが用いられるが、最近では放射光を用いた高分解能、微小部分析などを特徴とした方法の利用も拡大している。
一般的な装置の構成を図2に示す。前述のAlやCuをターゲットとしたX線銃と、その照射によって発生した光電子をエネルギー分光するための分光器、そして、分光された光電子を検出する検出器で構成されている。検出器は標準的にはいわゆる光電子増倍管タイプであるが、最近ではイメージングプレートを検出器として、測定と同時にイメージを得ることを可能としている装置も増えている。そして、試料も含めてX線や光電子の行路は全て10-7Pa以下の超高真空環境に置かれている。これは、いくつかの理由があるが、X線や光電子の減衰を防止する、試料の汚染を防止するなどが挙げられる。
XPSの検出深さが数nm程度と極めて表面に敏感な手法であるという特徴は、図に示す通り光電子を検出対象としていることによる。プローブとして用いられるXPS線は、誰もが知る通り透過力が極めて高く、当然ながら桁違いに深い領域まで侵入している。したがって、XPSの検出深さよりも深部でも光電子は発生している。しかし、XPSで検出される運動エネルギーの光電子は通常の媒質中では数nm程度の平均自由行程しか持っていないため、測定深さがその領域に限定されて極表面分析が実現できる。
XPSは高い表面感度だけでなく、原子の置かれている環境(化学状態)によって電子状態が変わることからピーク位置がわずかにシフトすることを利用して、化学構造解析を行うことができる。実際には、各化学状態に相当する成分をガウス関数やローレンツ関数、または、これらの加算関数で近似し、ピーク分離を行うことによってそれぞれの成分の割合を算出することになる。
また、光電子の放出効率(感度因子)は元素ごとに理論計算可能なことから、基本的には標準試料無しで定量分析を行うことが可能である。実際には、装置関数も考慮した感度因子が装置に付属していることが多いので、一般的にはこれを用いることになる。ただし、厳密には酸化物と金属など一部の
全文:約5031文字