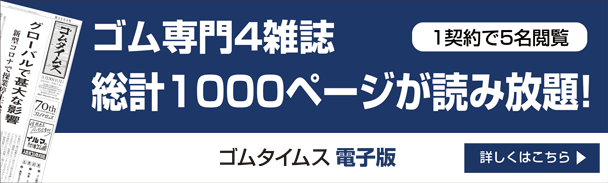山口大学大学院医学系研究科消化器・腫瘍外科学講座とUBEは2月6日、消化器がんに対する免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を強化する新規複合がん免疫療法の共同研究を開始したと発表した。
同共同研究では、がん細胞周辺の免疫環境(腫瘍微小環境)を「免疫学的にHotな状態」へと誘導する戦略を構築し、より幅広い患者層での有効性向上を目指す。
近年、がん免疫療法は消化器がんを含む多くの悪性腫瘍に対して有望な治療法として注目を集めている。特に免疫チェックポイント阻害剤は、がんが免疫細胞から逃れにくくする治療薬だが、現状では効果が明確に認められるのは患者全体の2~3割程度にとどまる。その理由の一つが、多くのがん組織が「免疫学的にColdな状態」にあり、免疫細胞が十分に活性化されない点となる。
消化器・腫瘍外科学講座は山口大学大学院医学系研究科免疫学講座(玉田耕治教授)と連携し、腫瘍内部の免疫反応を積極的に活性化できる複合免疫製剤の開発を行ってきた。
消化器・腫瘍外科学講座が実施した臨床試験では、同複合免疫製剤を投与した肝細胞がん患者のおよそ6割で、がん内部が「免疫学的にHotな状態」である事が明らかになった。この結果は、同複合免疫製剤の投与のない肝細胞がん患者での割合(約2~3割)を大幅に上回り、この製剤が腫瘍微小環境を免疫細胞に有利な方向へ変えることを示唆している。
さらに、動物実験(大腸がんモデルマウス)における基礎研究では、同複合免疫製剤を用いることで、免疫チェックポイント阻害剤(例、抗PDー1抗体)の使用量を抑えつつ同等の治療効果を得られる可能性が示唆された。これは患者への薬剤負担軽減にもつながる点で注目される。
同共同研究では、UBEが有する先端的な化合物と消化器・腫瘍外科学講座が開発してきた同複合免疫製剤の組み合わせにより、消化器がん組織内部へのより多くの免疫細胞浸潤やその活性化の促進を図る。これにより、特定の患者群に限らず、より幅広い患者層で免疫チェックポイント阻害剤が十分な効果を発揮することを目指す。
同共同研究から得られる知見や技術は、これまで治療効果が限定的だった患者にも、より有効な免疫療法を提供できる可能性を広げる。また、基礎研究から臨床応用への橋渡しとして、地域医療の発展や社会全体の健康向上に寄与することが期待される。
2025年02月07日