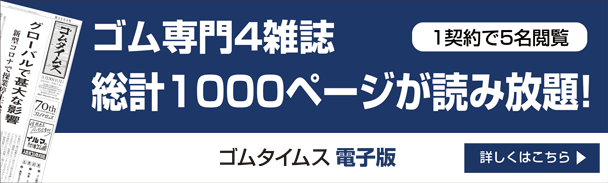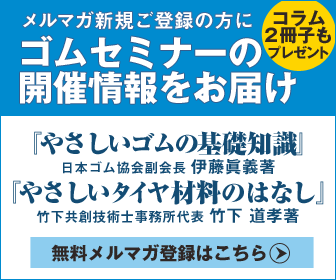ゴム・樹脂専門の技術ポータルサイト「ポリマーTECH」
表面処理の基礎的考え方とその評価法
~表面と接着、接着の基本、接着強度、表面処理、表面処理に伴う分子構造の変化、処理表面のキャラクタリゼーション、実例~
受講可能な形式
趣旨
最近ではプラスチックやゴムが単独で用いられることは少い。例えば、食品包装袋にしても水を通さないこと、酸素を通さないこと、強度がある程度あることなどの条件を満たすには、いろいろな特性のプラスチックフィルムを重ねて使用しなければならない。当然それらは密着していなければならない。また、自動車材料のようなものであれば、硬さと強度がある程度あって紫外線にも強く、また多くの場合耐油性にも優れていなければならない。あるいはプリント基板のようなものであれば、金属との接着性が優れていなければない。ここに、異種材料を接着する技術の必要性が生じてくる。残念ながら多くのプラスチック・ゴム類はそのままでは接着剤を用いても十分な接着力を持たない。ここに表面処理技術が必要になってくる。つまり、材料表面に極性官能基を付与して、接着剤が十分機能するような状態に改質する必要性が生ずる。
表面処理技術は多数存在するが、それらには一長一短があるため、目的によって取捨選択しなければならない。多くの場合装置を使用して表面処理が行われる。ところが、装置メーカーは機械や電気の専門家であり、材料の特性まではあまり把握していない。したがって、どの表面処理法を選ぶかは、あくまでも、使用者であるプラスチックやゴムを扱う技術者が判断しなければならない。ここに、プラスチックやゴムの技術者が表面処理技術を理解しておく必要性が生ずる。
表面処理法には物理的な方法で表面にエネルギーを与えて、カルボキシル基のような官能基を付与する場合と、シランカップリング剤や発煙硫酸を用いて官能基を付与する化学的な方法がある。
前者の方が後者よりもはるかに高速処理できるので、前者の方法が圧倒的に採用されている。
受講対象者
20~40代の研究開発に携わっているプラスチック・ゴム関連の技術者
| 日時 | 2025年10月17日10:30~16:30 |
|---|---|
| アーカイブ視聴 | 2025年10月23日~2025年11月6日 |
| 講師 | 小川俊夫(金沢工業大学名誉教授(金沢高分子ラボ 代表)) |
| 講師略歴 | 横浜国立大学工学部修士課程修了 |
| 受講料 | 45,000円/1名 |
| 会場 | WEBセミナー(ZOOM) |
| 主催会社 | ゴムタイムス社 |
| 配布方法 | PDFのテキストで配布 ※本セミナー資料の無断転載、二次利用、講義の録音・録画などの行為を固く禁じます。 |
| お申込み | このセミナーに申込む |
| 注意事項 |
※アーカイブ配信のみご希望される方は、「このセミナーに申込む」より【アーカイブ配信のみ】となっている方をお選びください。 ※アーカイブ配信実施セミナーの場合、リアルタイム視聴でご受講される方は、無料で「アーカイブ配信」を閲覧できます。振り返り学習に活用ください。 |
プログラム
1. 表面と接着
1. 1 接触角とYoungの式
1. 2 ぬれと表面張力
1. 3 ぬれと官能基
1. 4 官能基の極性
2. 接着の基本
2.1 分子間力
2.2 化学結合力
2.3 凹凸効果
3. 接着強度
3.1 接着の条件
3.2 接着強度
3.3 水分効果
3.4 表面脆弱層(WBL)
4. 表面処理
4.1 表面処理の基礎
4.2 コロナ放電処理
4.3 低圧プラズマ処理
4.4 大気圧プラズマ処理
4.5 紫外線処理
4.6 火炎処理
4.7 シランカップリオン剤処理
4.8 グラフト化処理
5. 表面処理に伴う分子構造の変化
5.1 空気雰囲気
5.2 不活性ガス雰囲気
6. 処理表面のキャラクタリゼーション
6.1 X線光電子分析法(XPS)
6.2 全反射赤外分光法(ATR)
6.3 原子間力顕微鏡法(AFM)
7. 実例
7.1 LDPEとPETの接着
7.2 芳香族ポリイミドフィルムと銅箔の接着
7.3 PVAcの表面処理
注意事項
セミナーの録画・撮影・テキストの複製は固くお断り致します。本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信対応セミナーとなります。
Zoom(ズーム)のやり方などでお困りの方は、セミナー当日までに設定や使い方をご指導致します。