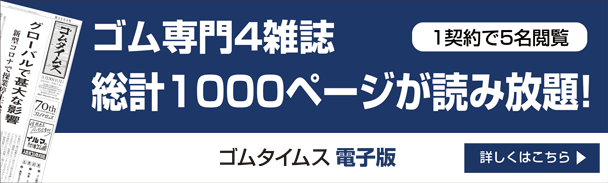専門技術団体に訊く7
日本化学工業協会 進藤秀夫専務理事
*この記事は2022年5月発行、ポリマーTECH Vol.13に掲載されました。
化学産業のCNに対する取り組み骨子を定める
持続可能な社会の実現に向けて貢献
一般社団法人日本化学工業協会(以下、日化協)は、2021年5月「カーボンニュートラル(以下、CN)への化学産業としてのスタンス」を策定し、化学産業のCNに対する取り組み骨子を定めました。日化協の進藤秀夫専務理事に改めて同協会の活動内容やCNの取り組みなどを聞きました。
──日化協の概要を教えてください。
日化協は「化学産業の健全な発展のための環境作り」と「我が国経済の繁栄と国民生活の向上」を目指し活動する、企業会員180社と団体会員80団体で構成される団体です(2022年2月時点)。たとえば保安・保全、技術、環境問題など共通の課題ごとに、環境安全委員会をはじめ、化学品管理委員会、レスポンシブル・ケア委員会など8つの委員会を組織しています。これらの委員会で会員の知見や情報を収集して整理し、会員にフィードバックします。また委員会の下に、ワーキンググループを作り、活動することもあります。
さらに、行政官庁に提言したり、関係団体と連携して会員と情報交換も行います。そのほか、国際化学工業協会協議会(ICCA)に参加し国際的に発信も行います。
──現状の重点目標については。
化学産業が、社会に必要とされる製品を安定的に提供し、社会の信頼に応えていくため、2020年5月から「製造時」「製品自体」「使用後」という3つの段階での「安全と環境に対する配慮」を重点テーマとして掲げています。
「製造時の安全と環境に対する配慮」では、工場の保安や安全の確保と、操業における環境負荷への最小化に継続して努めることが、引き続き最重要テーマです。保安・安全の確保の面では、事故情報得られる教訓やベストプラクティスの共有化を引き続き進めるとともに、設備の老朽化や現場の熟練作業員の高齢化などに対応しつつ、スマート保安への取り組み支援などを進めています。
「製品自体の安全と環境に対する配慮」については、化学品質管理を中心にサプライチェーンを通じたリスク管理に取り組んでいます。グローバルで共通な課題については、国際連携を強化し、社会課題に対するソリューションプロバイダーとして取り組んでいます。
最後の「使用後の安全と環境に対する配慮」ですが、循環型社会を構築するために重要かつ不可欠な取り組みとして、ケミカルリサイクルを成立・普及させるための技術開発や社会実装を積極的に推進していきます。
──化学産業の規模は。
「プラスチック製品」と「ゴム製品」も含めた広義の化学工業は、製造業全体で2019年の出荷額は約46兆円で国内第2位、付加価値額は18兆円で国内第1位の規模となり、日本の製造業に大きく貢献をしている産業です。また、天然物を代替する素材の開発、高機能な素材の開発は、社会や経済発展に貢献してきました。一方、公害問題の克服技術の開発や省エネ素材の開発などは、資源や環境問題解決に貢献しています。
また製造業全体で、化学工業の従業員数は約95万人にのぼり、雇用面でも国民生活を支えております。
──カーボンニュートラルへの取り組みについて。
日化協は2021年5月に「カーボンニュートラルへの化学産業としてのスタンス」を策定しました。そのスタンスは、「化学産業におけるGHG(温室効果ガス)排出削減」、「製品・サービスを通じたGHG排出削減貢献」を骨子としています。
化学産業の生産活動におけるGHG排出源として、化石資源の原料の使用や自家発電設備等の化石燃料の使用に伴うGHG排出などがあり、原料由来とエネルギー由来の2つの排出削減が求められています。エネルギー由来のGHG排出削減の取り組みとしては、革新技術の導入や自家発電設備の燃料切り替え、購入電力への切り替えなどが挙げられます。
原料由来の排出では、原料を化石資源から、バイオマス、プラスチック廃棄物、CO2・水素などに転換していくことが必要です。現在は、新たな原料プロセスへの大型投資を進めつつ、国際協力の維持や強化を追求するといった大変革の時期に突入しているのではないでしょうか。
製品・サービスを通じたGHG排出削減貢献は、化学産業自らの排出削減と並ぶ、もう一つの化学産業のCN達成への役割です。化学製品には、たとえば、軽量化材料、グリーンエネルギー創出に必要な素材などのように、使われる場面でGHG排出削減に貢献できるものが多くあります。LCA(ライフサイクルアセスメント)などライフサイクル全体での評価方向を定めることも大事になっていきます。
また、化学産業がCN達成に取り組むにあたり、政府への要望もまとめました。安定かつ安価なユーティリティの供給の拡大、従来技術の高効率化や省エネルギー化等の低炭素化に向けたインセンティブの付与のほか、研究開発の支援も必要です。CNを実現するためにも、研究開発への投資、設備投資や燃料・材料資材の選択などにおけるコスト上昇を社会全体で負担する、国際的に整合性の取れた仕組みの構築を進めることが重要になってきます。
──最近のカーボンニュートラルのトッピクスは。
2月10日に開かれた自民党政務調査会の総合エネルギー戦略調査会が設置した「2050年カーボンニュートラルに向けたエネルギー・産業構造転換プロジェクトチーム」に、日化協の森川宏平会長が参加しました。森川会長は、CNへの移行に向けたコストを社会全体で負担する政策の必要性を訴えたほか、化学産業のCNへの取り組みを説明し、政府支援を要望しました。
──「10月23日は化学の日」とは。
2013年に日化協をはじめ、日本化学会、化学工学会、新化学技術推進協会の4団体は、10月23日を「化学の日」に制定しました。毎年、化学の啓発と化学産業の社会への貢献の理解促進のためのイベントを開催しています。21年は、「2050年カーボンニュートラルの実現―地球規模の課題に取り組む化学系学協会―」というテーマで、パネルディスカッションをオンライン形式で開催しました。
──刊行物による情報発信について。
化学産業をアピールすることも日化協にとって、大事なひとつの役割です。日本の化学産業に関する各種統計データをグラフで分かりやすく解説した「グラフでみる日本の化学工業」を毎年発行しています。また、日化協の活動を網羅的にまとめた「日化協アニュアルレポート」も毎年発行し、化学産業の取り組みへの理解促進を図っています。
*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。