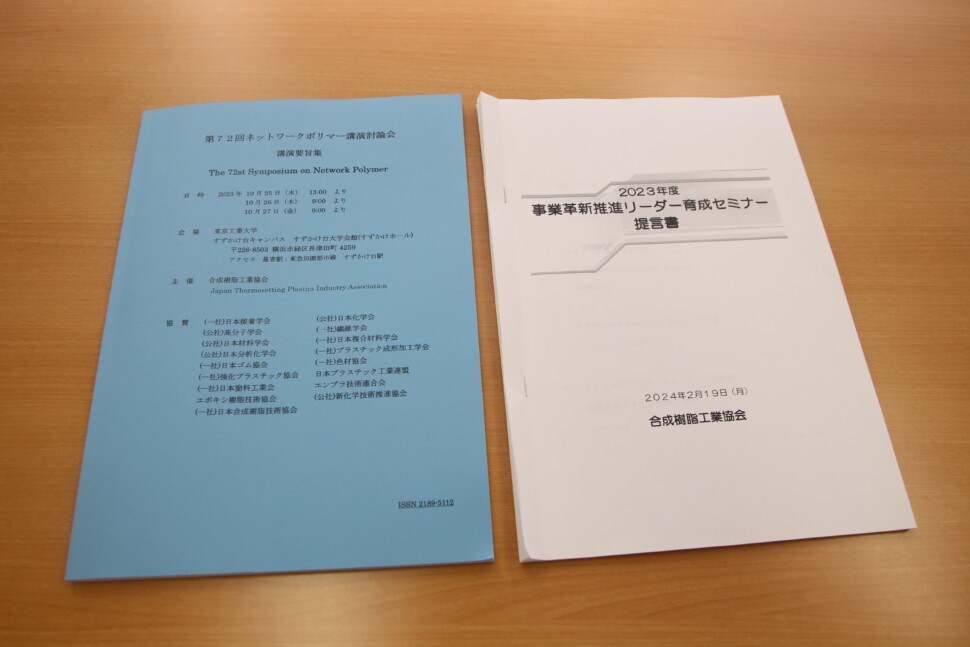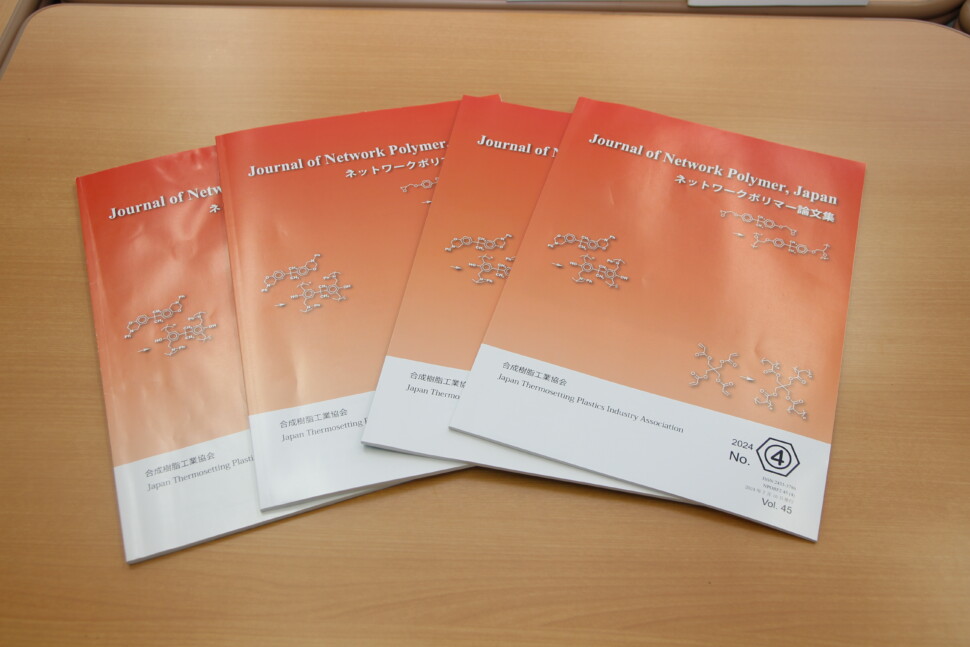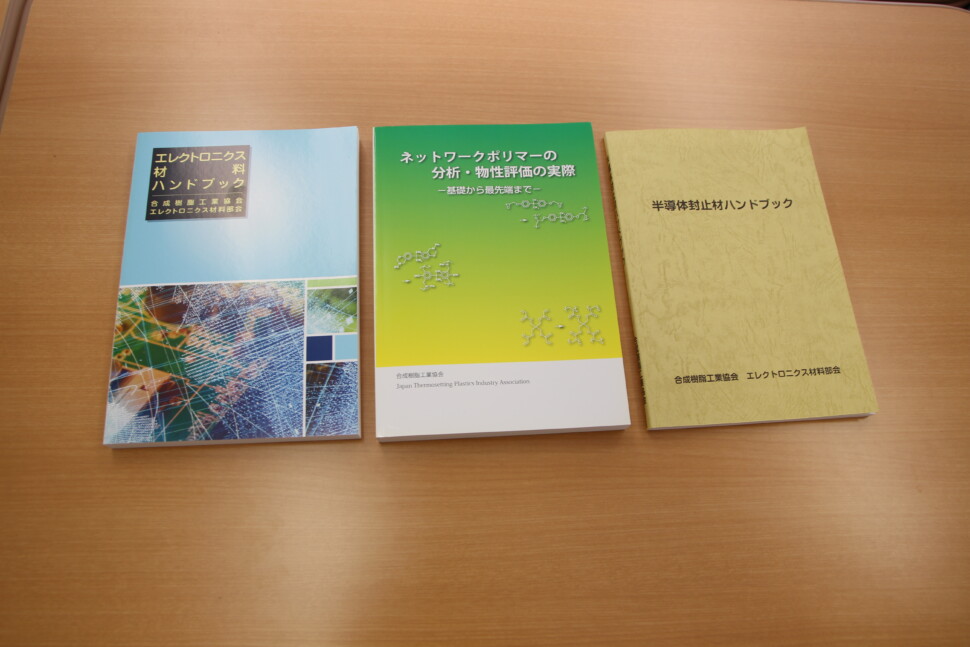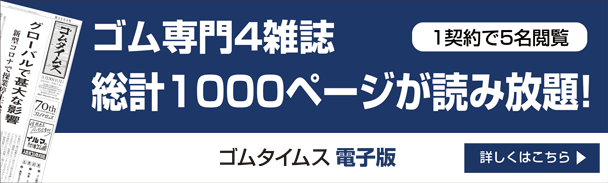専門技術団体に訊く15 団体インタビュー
合成樹脂工業協会 杉本利彦専務理事
合成樹脂工業協会は、国内の熱硬化性樹脂の製造者らによる業界団体であるとともに、学術活動にも取り組んでいます。長い歴史のある業界団体として、23年に設立70周年を迎えました。同協会の杉本利彦専務理事に同協会の歴史や事業の取り組みについてお聞きしました。
──合成樹脂工業協会の歴史について
当協会は1953年(昭和28年)に設立しました。おかげさまで、2023年で創立70周年を迎えることができました。会員数は、役員会社5社を含む、現在44社となっております。
当協会は、熱硬化性樹脂及びその関連製品に関わる規格標準化、環境、製品安全、統計など様々な取り組みを行っています。その一方で、産・官・学の緊密な連携を活かし、講演討論会の開催や学術誌「ネットワークポリマー」の発刊、人材育成などの学術活動にも注力しています。
それらの活動をする為協会には、学術特別部会、フェノール樹脂・アミノ樹脂成形材料
部会、積層板部会、フェノールレジン部会、接着剤部会、メラミン樹脂化粧板部会、不飽和ポリエステル樹脂部会、塗料用合成樹脂部会、エレクトロニクス材料部会、環境・リサイクル研究部会、電気材料規格部会、ポジティブリスト対応部会、電子機能材料部会があります。
──同協会の特長を教えてください。
他の業界団体と違う点は、一般的に業界団体は規格などの団体活動が中心ですが、当協会は学会活動にも積極的に取り組んでいるところです。
例えば、ネットワークポリマー講演討論会は、当協会の設立の2年前、1951年に、フェノール樹脂討論会(現:ネットワークポリマー講演討論会)として開催されていました。これを当協会が引継ぎ、年1回開催しています。今年も10月に近畿大学で第73回ネットワークポリマー講演討論会を開催しました。
──ネットワークポリマー論文集とは。
45年前から論文集を年6冊、2カ月に1回発行しており、歴史のある論文集になっています。大学の先生ら12人で構成されている編集委員会が担当し、学術論文を掲載しています。コロナ禍でも無事に論文集の発行を止めることなく、発行できました。
そのほか、出版活動にも注力しており、合成樹脂のテーマにあった『半導体封止材ハンドブック』や『エレクトロニクス材料ハンドブック』なども出版しています。
──人材育成にも力を入れているとお聞きしましたが。
プラスチック業界では、規格などが欧州中心に進められている現状があります。それに対して、業界として、会員各社は競合会社でもありますが、我が国の国際競争力を強めるためにも、会社の垣根を超えてネットワークを構築することが重要になっています。そのため、当協会は人材育成にも注力しています。それが毎年開催している「人材育成セミナー」です。
毎回、約20人が参加しています。会社がそれぞれ違う30代が中心となり、チームで新規事業提言書をまとめる事で事業革新を推進できるリーダーの育成を目指しています。その報告会も実施しています。今年で18回目を迎え、卒業生も350人以上となり、最近では同窓会も開きました。
第18期人材育成セミナーでは5回トップ講演と4回の特別講演を予定しています。
トップの講演では、役員会社5社をはじめとする協会会員会社トップの方々にお話を頂戴します。8月は、三菱ガス化学株式会社の代表取締役社長藤井政志氏に講演をしていただきました。
トップ講演は、各会社の代表の講演を聞くことはなかなかない機会ですので好評です。人材育成セミナーの講演は、人材育成セミナーに参加している人のほか、協会内外の多くの人に参加して頂けるよう、オープン聴講という形を取っています。
──現在の課題がありましたら教えてください。
業界として、熱硬化性樹脂の市場が減少していることです。これが一番大きな課題です。人口減少局面にある日本市場で自動車の国内生産や住宅需要が縮小しています。
その結果、熱硬化性樹脂の数量も減っていきました。現在は付加価値が高められるパッケージ分野や環境対応材料に注力しています。しかし、全体的な数量は減少傾向になっています。
──今後の展開について。
数量が減少している熱硬化性樹脂ですが、新たな着眼点を持つことで、より多くの需要を見出すことができると思います。熱硬化性樹脂の用途を更に広めていくためにも、協会として何ができるかをということを協会メンバーと一緒に考えていきたいと思います。
*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。